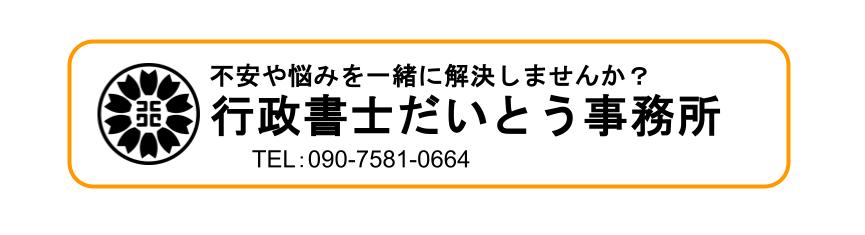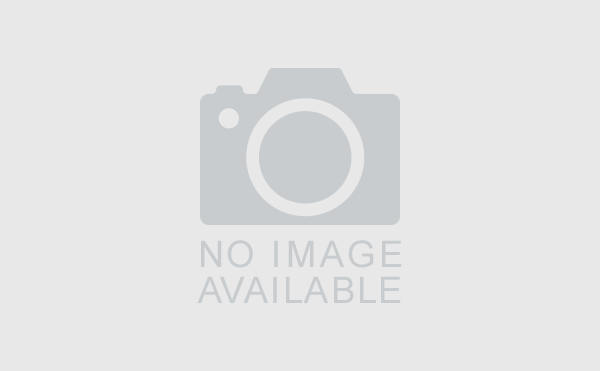対話で分かる遺言相続!(相続編)

対話で分かる遺言相続!(相続編)へようこそ!
行政書士のだいとーです!よろしくお願い致します!

やじろーといいます。
遺言相続って言葉を最近よく耳にするんだけど、
実はあまり内容が分かってなくて・・・。
色々と教えてくれませんか?

勿論です!
確かに、最近ではテレビや新聞などで相続問題や相続トラブルが取り上げられたりもしていますよね。
主に中高齢の方は不安になるでしょうし、遺言相続のうち相続について基本からお教え致します。
釈迦に説法の部分もあるでしょうが、どうぞよろしくお願い致します。

一から学びなおすつもりです!
こちらこそよろしくお願いします。

まずは、相続についてお話しします。
亡くなった方を被相続人といいますが、被相続人の資産・負債を相続人のものにすることを「相続」といいます。
相続は、被相続人が亡くなったときに開始します。
現金や預金、不動産、自動車、株、投資信託などの資産のほか、銀行からの借入金、保証債務も相続することになります。

借入金も相続することになるんですね・・・。
保証人になったことはないので、保証債務は心配していないんだけど、住宅ローンがちょっと残っているのが気がかりです。

住宅ローンの場合は団信(団体信用生命保険)がついていないかを確認してみればいいと思いますよ。
団信がついていれば、住宅ローンがチャラになるかもしれませんからね!

また確認しておきます。

さて、相続の話の続きですが、法律上では相続人は決められているのです。

私には、妻と子どもが2人いるんですが、妻と子どもが相続人になるんですよね?

その通りです!
後ほど詳しくお話ししますが、遺言書を作成していない場合は、法定相続人が相続することになります。
法定相続人は家族構成によって変わるのですが、まず配偶者は相続人になります。
次に子どもがいれば子どもも相続人になります。
子どもが既に亡くなっていれば孫が、そもそも子どもがいなければ、被相続人の父母が相続人になります。
子どもも父母もいなければ、被相続人の兄弟姉妹が、その兄弟姉妹が亡くなっていれば、甥や姪が相続人になります。
子どもの代わりに孫が相続することや、兄弟姉妹の代わりに甥姪が相続することを、代襲相続といいます。

ややこしいですね・・・。

言葉ではなかなか理解するのが難しいかもしれませんね。簡単な図を作成してみました。法定相続ですと、以下の7パターンになります。
| 相続人の構成 (法定相続人) | 法定相続割合 | 遺留分 |
|---|---|---|
| ①配偶者のみ | 100% | 2分の1 |
| ②子どものみ | 100% | 2分の1 |
| ③被相続人の父母のみ | 100% | 3分の1 |
| ④被相続人の兄弟姉妹のみ | 100% | 遺留分なし |
| ⑤配偶者と 子ども | 配偶者:2分の1 子ども:2分の1 | 配偶者:4分の1 子ども:4分の1 |
| ⑥配偶者と 被相続人の父母 | 配偶者:3分の2 父母 :3分の1 | 配偶者:6分の2 父母 :6分の1 |
| ⑦配偶者と 被相続人の兄弟姉妹 | 配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1 | 配偶者:2分の1 兄弟姉妹:遺留分なし |

なるほど・・・法定相続人は分かりました!
ところで、横に書いてある「法定相続割合」と「遺留分」って何ですか?

よく気づいてくれましたね!
法定相続割合とは、民法で定められている相続財産の取得割合です。
絶対にこの割合で相続しなければならない、というものではなく、あくまで相続する割合の目安になっています。
①~④の場合は、他に相続人がいないため、全財産を相続することができます。ただし、②のように複数人いる場合もあります。その場合は、年上・年下などは関係なく、人数で頭割りとなります。
やじろーさんの場合は、⑤に当てはまりますので、配偶者様が相続財産の2分の1を、お子さま2人はそれぞれ4分の1を相続することになります。

なるほどね。
仮の話なんだけど、妻が子どもを身ごもっていたときはどうなるのでしょうか?
やっぱり生まれていないから、相続人にはならないのかな?

いえ、じつは胎児も相続人になります。民法上でも「胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす」と規定されています。
ただし、「胎児が死体で生まれたときは、適用しない」とも規定されているので、無事に生まれてきたときに、遡って相続することになります。

そうなんですね。
ところで、遺留分ってなんなんですか?

遺留分は、簡単に言うと配偶者や子ども、被相続人の父母だけに認められた最低限の相続財産の取り分です。
例えば、遺言書に「(配偶者ではない)Aさんに相続財産の全てを遺贈する」と書かれていたとしましょう。被相続人の意志とはいえ、被相続人の配偶者からすると「長年一緒に過ごしてきたのに、相続財産が手に入らないなんて・・・」と思うかもしれません。そもそも生活が成り立たなくなるかもしれません。
そういったことを防ぐ為に、最低限の取り分である遺留分があるのです。

たしかに、相続人が全く相続財産を相続出来なければ、
相続人は可哀そうですよね。

ちなみに、遺留分を無視した遺言内容も問題ありませんが、遺留分が認められている相続人から遺留分侵害額請求権を行使されるかもしれません。
遺留分を侵害している場合は、金銭で遺留分を請求することが出来ます。

遺留分侵害額請求が出来るのなら、相続人からすると安心ですね!

とはいえ、遺留分侵害額請求も手間がかかりますからね・・・。
遺留分について主に問題になるのは遺言書を作成するときです。
遺言については、また改めてお話しします!

ところで、借金も相続することになるんだったよね?
絶対に相続しないといけないのかな?

もし多額の借金も相続することになると不安になりますよね。
そこで、相続人には相続時に3つの選択肢があります。
1つ目は「単純承認」です。単純承認とは、相続人は資産も負債も全て相続します。
自分が相続人であることを認識してから3ヵ月以内に「限定承認」や「相続放棄」を行わないと、単純承認をしたとみなされます。
特に何の手続きも必要なく、相続することになるので、手間がかからないというメリットはありますが、思ったより相続する借金が多額だった場合は、逆に自分の資産で借金を返済することにもなりかねません。

つまり、相続が発生したときには、被相続人にどれくらいの資産や負債があるかをしっかり調べないといけない、ということですね!

その通りです!そのため、遺言者は、どれくらいの資産・負債があるかを財産目録として残しておくことが望まれます。財産目録を見れば、相続人は、被相続人の資産・負債の確認をしやすいですからね!
預金がいくらある、借金がいくらある、までは記載しなくても大丈夫でしょう。預金していたり借入している金融機関さえ分かれば、相続人は残高照会出来ます。

財産目録が無ければ、相続財産がどれくらいあるかを調査することは大変そうですね・・・。

いろいろな資料を見ないといけませんので、結構骨の折れる作業ですね。
さて、2つ目の選択肢は「限定承認」です。
限定承認とは、相続した資産の範囲内で負債を相続する、というものです。つまり、借金が思ったより多くても、相続した資産の分までしか支払わないので、自分の資産から借金を返済しなくても良いのです。最悪、相続財産がゼロになるだけ、というものです。

それは良いですね!
でも、デメリットもあるんでしょう?

その通り、デメリットもあります。
まず、相続人全員が限定承認を選択しなければなりません。つまり、1人でも単純承認や相続放棄を選択すると、他の相続人は限定承認を選択することが出来ません。
また、家庭裁判所に申述が必要であること、公告や清算で手間と時間がかかることから、限定承認を選択する人は少ないのが実情です。
それでも、思いのよらない被相続人の借金に備えたりしたい場合は限定承認を選択することも良いでしょう。

では、相続した多額の借金から逃れる方法はないんですか?

3つ目の選択肢として、「相続放棄」があります。
相続放棄は、相続があったことを知ってから3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要がありますが、限定承認と違い、その相続人1人で相続放棄を行うことが出来ます。
相続放棄の効果として、相続財産の一切を相続しなくなります。たとえ、どうしても相続したかった不動産があったとしても、相続出来ません。その代わり、被相続人に借金があった場合は、債権者に相続放棄した旨を主張し、借金を返済する必要はありません。

なるほど。
被相続人の借金が多額の場合は、多くの人が限定承認よりも相続放棄を選択しているんですね!どっちにしろ資産が手に入らないのなら、相続放棄のほうが手続きが比較的少ないですしね。

ただ、相続放棄で注意しないといけないのが、他の相続人への影響です。

他の相続人への影響ですか?
どんな影響があるんですか?

相続放棄をすると、その人は相続人ではないものとして扱われます。
例えば、被相続人に配偶者と子ども、被相続人の父母がいるとしましょう。法定相続人は配偶者と子どもですが、子どもが相続放棄をするとどうなるでしょうか?

子どもが相続人ではない扱いになるので、配偶者と被相続人の父母が相続人になるのですか?

その通りです!よくご理解されていますね!
ちなみに、先ほどの例で配偶者が相続放棄をすると、相続人は子どものみになります。

なるほど、相続放棄をするときは、次の相続人がいるかどうかも考えたほうが良いんですね。
他の家族に被相続人の借金を背負わせることにもなりかねないですもんね!

そうです!
それがきっかけで親族間で仲違いが起きる可能性もありますから、気をつけたいところです。
ちなみに、事実上の相続放棄というものもあります。

なんですか?相続放棄と違うものなのですか?

遺言書が無ければ、相続人は遺産分割協議を行う必要があります。要するに、どの遺産を誰が、どのくらい相続するか、を協議するのです。
そこで、ある相続人が「私の相続分はゼロでいいよ、ただし借金も相続しないからね」ということで、実質的に資産負債を受け取らないことで協議がまとまったとします。

それなら手軽で良いですね!家庭裁判所への申述も不要でしょう?
何か問題あるんですか?

確かに、家庭裁判所への申述も要りませんが、借金がある場合には問題になるんですよ。
銀行などの債権者は、遺産分割協議書で決めたことに関係なく、借金の返済を求めることが出来るんです。
ですので、被相続人が借金していた場合は、相続放棄をしたほうが良いでしょうね。

いろいろ気をつけないといけないことがあるんですね・・・。

相続について詳しく知っている方は少ないので、機会があれば専門家などのセミナーを受けてみるのも良いかもしれませんね。
相続についてのご説明は以上となります。どうでしょう?なんとなくわかりましたか?

ありがとうございました!
今まで、相続についてあまり考える機会もなかったので、非常に助かりました。また色々と教えてください!

それは良かったです。
私で良ければ喜んでレクチャーしますよ!今後ともよろしくお願い致します!