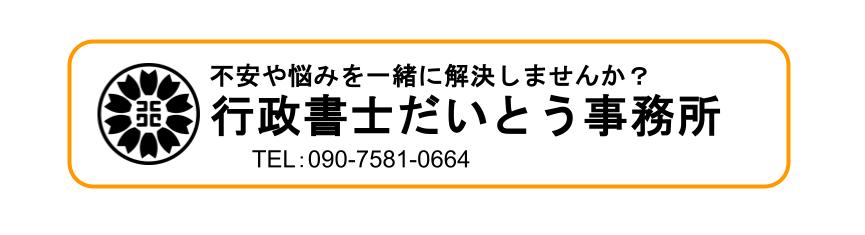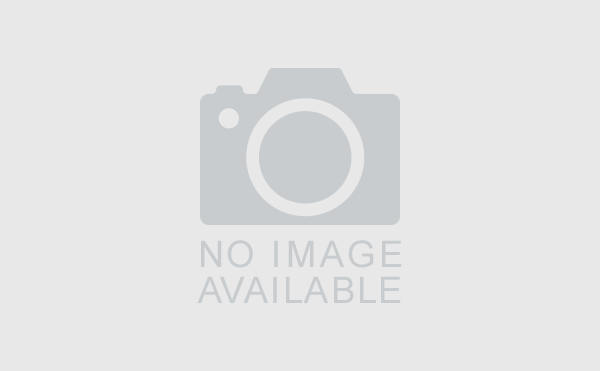遺言の撤回・修正|一部撤回・全部撤回の方法と注意点
遺言書を作成したものの、後日「内容を変更したい」「全部書き直したい」と思うことはよくあります。遺言書の撤回や修正は法律上認められていますが、手続きや方法を誤ると相続トラブルの原因になることも。
この記事では、遺言の撤回・修正方法や注意点を、自筆証書・公正証書の種類別に解説します。
遺言書は撤回・変更可能
遺言者が生存中であれば、遺言書の内容は自由に撤回・変更できます。撤回方法には次の2種類があります。
- 一部撤回:遺言内容の一部だけ効力を失わせる方法
- 全部撤回:遺言書全体の効力を失わせ、新しい遺言を書き直す方法
一部撤回の方法
新しい遺言で一部上書きする
一部撤回は、既存の遺言と抵触する部分だけを無効にする方法です。後から作成した遺言が優先されます。
例
- 元の遺言書:「〇〇銀行の預貯金全額をAに相続」「〇〇証券の株式全てをBに相続」
- 修正後:「〇〇銀行の預貯金全額をBに相続」
ただし、古い遺言書だけが見つかると相続人が混乱する可能性があります。可能であれば、全撤回して書き直す方が安全です。
財産の処分による一部撤回
遺言に記載された財産を売却・消費・贈与すると、その財産に関する遺言は撤回されたとみなされます。
実務上は、「株式・預金・投資信託・未収配当金など一切の財産」と包括的に記載することで、撤回リスクを回避できます。
全部撤回の方法
新しい遺言書を作成する
遺言書が複数ある場合は最も新しい遺言が優先されます。新しい遺言には、古い遺言を撤回する旨を明記すると相続人に分かりやすくなります。
遺言書を破棄する
- 自筆証書遺言:自筆証書遺言書保管制度を利用していなければ破棄で撤回可能
- 秘密証書遺言:破棄で撤回可能
- 公正証書遺言:公証役場で撤回手続きが必要
破棄方法は、シュレッダーや裁断が安全です。ゴミ箱にそのまま捨てると、他人に拾われる可能性があります。
公正証書遺言の注意点
公正証書遺言は公証役場で作成されるため、破棄だけでは撤回できません。撤回する場合は、公証役場で申述を行うか、新しい遺言にて古い遺言を撤回する旨を明記する必要があります。
実務上の注意点
- 一部撤回は簡単ですが、古い遺言書が残ると混乱の原因になる
- 全部撤回して新しい遺言を作成する方が相続人にとって分かりやすく安全
- 財産の処分や不明確な文言はトラブルの原因になる
- 遺言の撤回・修正は必ず遺言者本人が生存中に行う
- 撤回や修正の内容は明確に書面化し、相続人に誤解を与えない
よくある失敗例
- 古い遺言と新しい遺言が両方見つかり、相続人がどちらを有効とすべきか迷う
- 公正証書遺言を破棄しただけで撤回したと思い込む
- 財産を売却後、遺言内容が不明確になり混乱する
- 一部撤回だけで古い遺言が残り、相続人間でトラブルになる
まとめ
- 遺言書は作成後でも自由に修正・撤回可能
- 一部撤回より、全部撤回して新しい遺言を作成する方が安全
- 公正証書遺言は公証役場で手続きを行う必要がある
- 財産の処分や不明確な文言には注意
- 撤回・修正は明確に書面化し、相続人に混乱を与えない
遺言書の撤回・修正は法律上認められていますが、相続人に混乱やトラブルを招かないよう、明確で安全な方法で行うことが重要です。