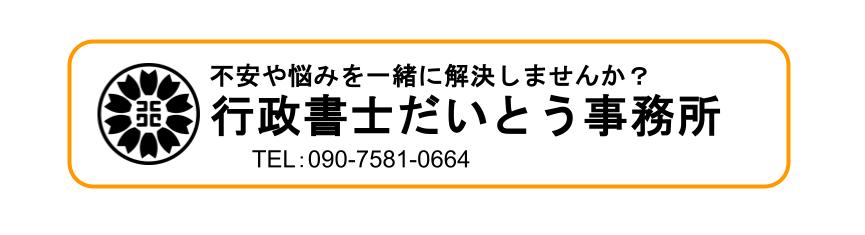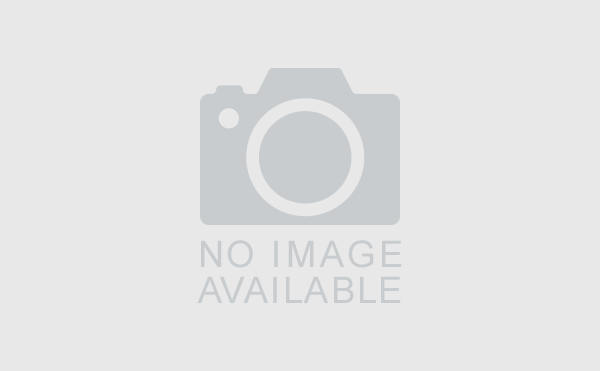保証人とは?種類とリスクをわかりやすく解説
融資や借入を受けるとき、「保証人をつけることが条件」と言われることがあります。
保証人とは、債務者が返済できない場合に代わって返済する責任を負う人のことです。
保証人にはいくつか種類があり、それぞれ役割やリスクが異なります。
ここでは、初めての方でもわかりやすく解説します。
保証人の基本
- 個人でも法人でも保証人になれます
- 複数人が保証人になることも可能
- 誰が保証人になるかは債権者と債務者の話し合いで決まることが多い
- 未成年者や判断能力のない人は保証人になれません
例:90歳の親を長期融資の保証人にするのは現実的に難しいです
保証人の種類
1. 通常保証人
債務者が返済できない場合に代わって返済する義務を負います。
保証人には以下の権利があります
- 催告の抗弁権:まず債務者から返済してもらうよう求められる権利
- 検索の抗弁権:債務者に十分な財産がある場合、まず債務者から回収するよう主張できる権利
- 分別の利益:保証人が複数いる場合、頭割りで返済できる権利
2. 連帯保証人
多くの場合、金融機関が求める保証人は 連帯保証人 です。
- 催告・検索・分別の利益は無し
- 債務者の財産や他の保証人の人数に関わらず、借金の返済義務を負う
- 実質的に「債務者と同じ責任」を負うため注意が必要
3. 根保証人
- あらかじめ定めた 極度額(上限) までの債務を保証
- 何度も借入・返済を繰り返す場合に便利
- 個人が根保証人になる場合は、極度額と元本確定期日を設定
- 元本確定期日を設定しない場合は、原則3年で元本確定
- 設定する場合でも最長5年
- 債務者や保証人が死亡した場合、破産手続き開始の場合なども元本が確定
4. 物上保証人
- 不動産や預金、株式、売掛債権など 物的担保 を提供して保証する
- 債務者が返済できない場合、担保を売却して返済に充てる
- 連帯保証人に比べてリスクは限定的
例:「お悩み:借入にあたってどんなものが担保に出来る?」もご覧ください
保証人が返済した場合(保証履行)
- 債務者が返済できない場合、保証人が代わりに返済することがあります
- このとき、保証人は債務者に対して 求償権 を行使可能
- 債務者は保証人に返済する義務がある
つまり、債務者は借入をしても逃げられない仕組みになっています。
まとめ
- 保証人には「通常保証人」「連帯保証人」「根保証人」「物上保証人」などの種類があります。
- 一般的に求められるのは 連帯保証人 で、実質的に債務者と同じ返済義務を負います。
- 保証人になる場合は、リスクや返済義務を十分に理解することが重要です。
奈良市で融資や保証人に関する相談なら
保証人や融資、資金調達について不安がある方は、奈良市の行政書士だいとう事務所 にご相談ください。
- 融資や保証人契約のポイント解説
- 金融機関への書類作成支援
- 中小企業・個人事業者の資金調達支援
初回相談は無料です。
安心して資金計画を進めるために、専門家と一緒に準備しましょう。