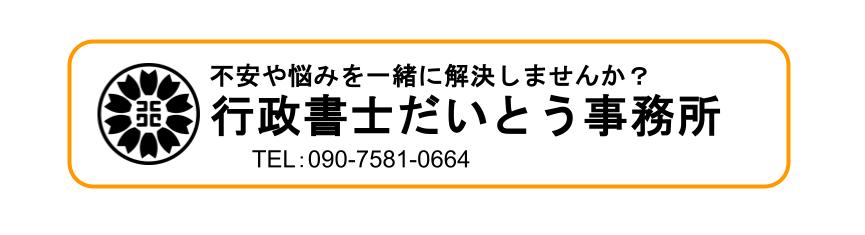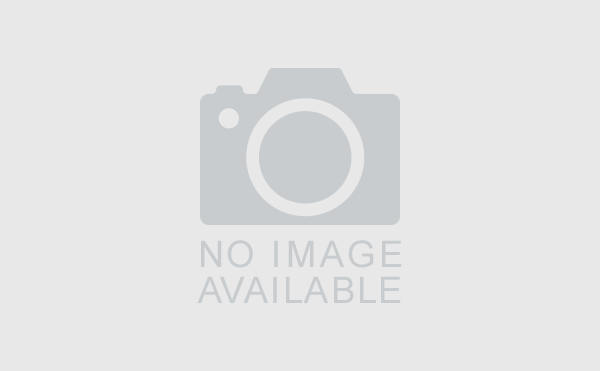財務の基本:貸借対照表の見方
中小企業経営者にとって、貸借対照表(BS)は会社の財務状況を把握するために欠かせない書類です。
この記事では、貸借対照表を正しく理解し、経営判断や事業計画に活かすためのポイントをわかりやすく解説します。
貸借対照表とは?
貸借対照表は、会社が保有する資産・負債・純資産の状況を示す書類で、次の5つの項目に分けられます。
- 流動資産
- 固定資産
- 流動負債
- 固定負債
- 純資産
貸借対照表の基本原則として、資産の合計 = 負債+純資産の合計が必ず一致します。
このバランスを確認することで、会社の財務健全性を判断できます。
貸借対照表の各項目
①流動資産
1年以内に現金化が見込まれる資産です。
- 現金・預金
- 売掛金・受取手形
- 商品・材料
- 有価証券
- 貸倒引当金(マイナス計上)
流動資産が流動負債を上回っていれば、短期の支払い能力は問題ありません。
②固定資産
現金化に1年以上かかる、または現金化を目的としない資産です。
- 有形固定資産:土地・建物・機械装置
- 無形固定資産:ソフトウェア、のれん(ブランド価値など)
- 投資その他の資産:投資有価証券、関連会社株式、子会社株式
固定資産の内容と価値を理解することは、長期的な財務健全性の判断に役立ちます。
③流動負債
1年以内に支払う必要のある負債です。
- 買掛金・支払手形
- 短期借入金・未払金
- 前受金(事前に受け取ったお金。サービス提供義務があるため負債に計上)
流動資産と比較して不足している場合、資金調達や資産の処分が必要になることがあります。
④固定負債
支払いまでが1年以上先の負債です。
- 長期借入金
- 社債
固定負債は返済まで時間的余裕がある一方で、返済原資を確保するために、購入した資産や事業収益とのバランスを確認することが重要です。
⑤純資産
会社の自己資本を示す項目です。
- 資本金・資本準備金
- 利益剰余金(設立からの累積利益・損失)
純資産がマイナスの場合は債務超過となり、金融機関からの借入が難しくなる可能性があります。
債務超過の主な原因は、赤字決算が続くことです。
資産・負債・純資産のバランス
- 流動資産 vs 流動負債
流動資産が十分であれば、短期支払いに問題なし。
流動負債が上回る場合は、固定資産の処分や借入で資金調達が必要。 - 固定資産 vs 固定負債
設備資金など長期借入金で購入した固定資産は、返済期間が長いためバランスが取れていれば問題なし。 - 純資産の多さ
純資産が多いほど経営の余裕があり、債務超過リスクが低くなります。
中小企業経営者へのアドバイス
- 赤字決算の分析
赤字の原因を把握し、売上向上策や経費削減策を検討する。 - 貸借対照表の定期確認
資産・負債・純資産のバランスを定期的に確認し、経営判断に活かす。 - 金融機関との関係
債務超過や借入状況を理解して、適切に融資相談や返済計画を立てる。
まとめ
貸借対照表は、会社の財務健全性や資金繰りの状況を把握するための基本ツールです。
弊事務所では、中小企業経営者が貸借対照表を理解し、経営判断や事業計画に活かすサポートを行っています。
中小企業経営者は、まず流動資産・流動負債・固定資産・固定負債・純資産のバランスを確認し、会社の財務状況を客観的に把握することから始めましょう。