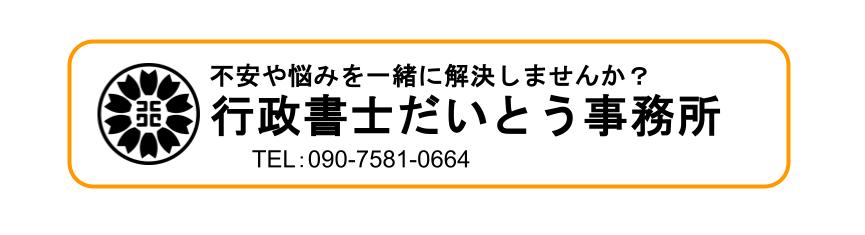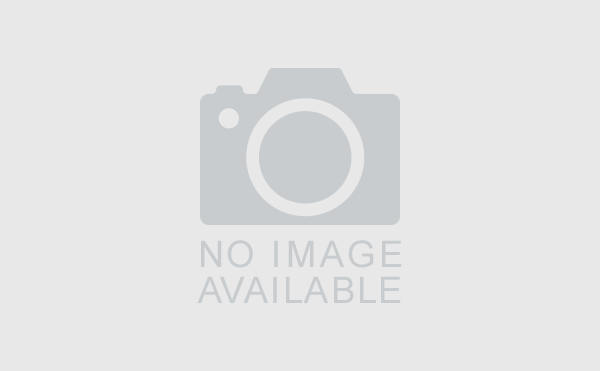知っておきたい相続税の基本
相続が発生すると、財産を引き継ぐだけでなく、相続税の手続きも必要になる場合があります。行政書士としては、相続税の申告や納付そのものは税理士の領分ですが、相続税の概要や手続きの流れ、必要書類の整理、税務署への申請準備サポートなどは関与可能です。
相続税とは?
相続税とは、被相続人(亡くなった方)の財産を相続や遺言で取得した場合に発生する可能性のある税金です。
誰が納めるのか
相続人や受遺者(遺言で財産を受け取った人)です。
申告期限
相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
申告不要の場合
財産が一定額以下で、基礎控除内の場合。ただし小規模宅地の特例や配偶者の税額軽減を受ける場合は申告が必要です。
手続きのポイント
課税対象となる財産の整理
- 現金・預貯金
- 不動産(土地・建物・立木など)
- 株式や投資信託などの有価証券
- 生命保険金や退職手当金(みなし相続財産)
非課税となる財産の確認
- 仏壇・仏具
- 法定相続人×一定額の生命保険金や退職手当金
奈良市・生駒市の税務署での申告
- 奈良市:奈良税務署
- 生駒市:生駒税務署
- 申告期限は10か月以内。必要書類(戸籍謄本、財産目録、固定資産評価証明書など)を事前に整理することが重要です。
不動産がある場合
- 名義変更登記は法務局で行います
- 相続財産目録や遺産分割協議書を整えることで、スムーズに手続きを進められます
行政書士がサポートできること
- 相続人の確認や戸籍謄本の取得
- 財産の調査・目録作成
- 遺産分割協議書の作成支援
- 必要書類の整理や提出補助
※相続税の計算や申告書作成そのものは税理士の領分ですが、行政書士は申告に必要な準備作業をサポートできます。
まとめ
- 相続税はすべての相続人が関わる重要な手続きの一つです
- 奈良市・生駒市では、税務署や法務局の手続きをスムーズに行うために、行政書士による書類整理・手続きサポートが有効です
- 相続税の具体的な計算や節税策は税理士に相談しつつ、行政書士は書類準備や相続人間の調整を支援することで、相続手続き全体を円滑にできます