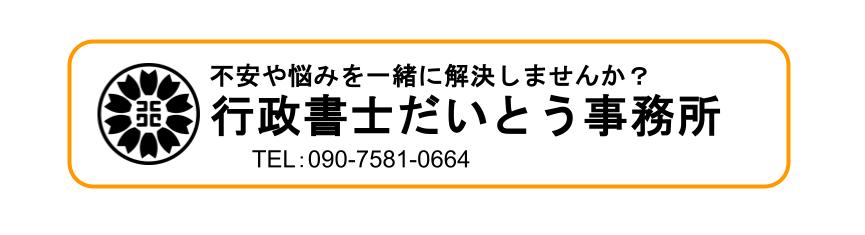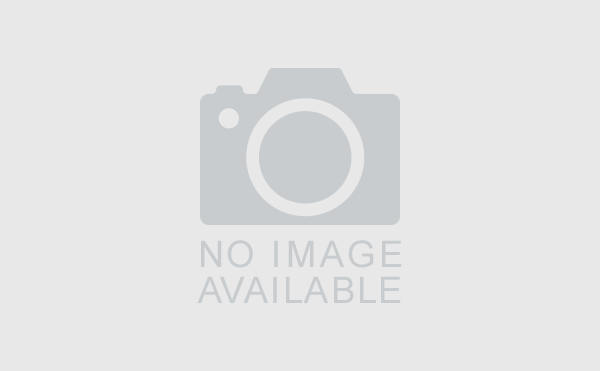相続放棄とは
相続が始まると、相続人は「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかを選択することになります。
ここでは、相続放棄について行政書士の立場からわかりやすく説明します。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人の資産や負債、権利・義務を相続する権利を放棄することです。
相続放棄をすると、初めから相続人ではなかったものとみなされます。
原則として、相続開始を知ったときから3ヵ月以内に家庭裁判所へ申述する必要があります。
限定承認と異なり、他の相続人の同意がなくても1人で行うことが可能です。
相続放棄を選ぶ主なケース
相続放棄を検討するケースとして、次のようなものがあります。
① 資産よりも負債が多い場合
被相続人に借金などの負債があると、単純承認ではそれも相続してしまいます。
負債を引き継ぎたくない場合、相続放棄を行えばその支払義務を免れることができます。
② 相続争いを避けたい場合
遺産の分け方をめぐり、相続人間で紛争が起こることがあります。
相続財産を手に入れない代わりに、トラブルに巻き込まれたくないという理由で相続放棄を選ぶ人もいます。
③ 特定の相続人に財産を承継させたい場合
民法上、相続人には順位があります。
先順位の相続人が相続放棄をすると、後順位の相続人が相続権を得ます。
例えば、相続人が配偶者と子の場合、子が放棄すれば次順位である被相続人の父母が相続人になります。
配偶者が「子に全て相続させたい」と思う場合も、相続放棄によってそれが可能になります。
④ 管理が難しい財産を相続したくない場合
山林や老朽化した建物など、維持・管理が困難な不動産を相続したくない場合にも相続放棄が選択されます。
一定の条件を満たせば「相続土地国庫帰属制度」を利用できる場合もありますが、費用や手間を考慮し、放棄を選ぶ人もいます。
相続放棄による紛争の可能性
相続放棄をすると、後順位の相続人に権利が移ります。
これはメリットでもありますが、トラブルの原因になることもあります。
たとえば、配偶者と子が相続放棄をすると、被相続人の父母(または兄弟姉妹)が相続人となり、多額の負債を背負うことになる場合があります。
その結果、「なぜ放棄したのか」と後順位の相続人から不満が出ることもあります。
相続放棄を行う前に、次に相続人となるのは誰かを確認しておくことが重要です。
事実上の相続放棄とは
遺産分割協議において「自分の取り分はゼロで良い」として、他の相続人に全て譲る方法があります。
これは家庭裁判所での手続きを経ないため、「事実上の相続放棄」と呼ばれます。
事実上の放棄のリスク
事実上の放棄は、あくまで協議上の取り決めであり、法的には相続人であることに変わりはありません。
そのため、被相続人に借金があった場合、債権者から返済を求められる可能性があります。
一方、家庭裁判所で正式に相続放棄をした場合は、初めから相続人でなかったものとみなされるため、債権者から請求を受けることはありません。
まとめ
- 相続放棄をすると、被相続人の資産・負債を一切相続しないことになります。
- 手続きは、相続開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。
- 相続放棄は1人で申述でき、他の相続人の同意は不要です。
- 事実上の放棄では債権者に対抗できないため、借金がある場合は正式な相続放棄を選ぶべきです。