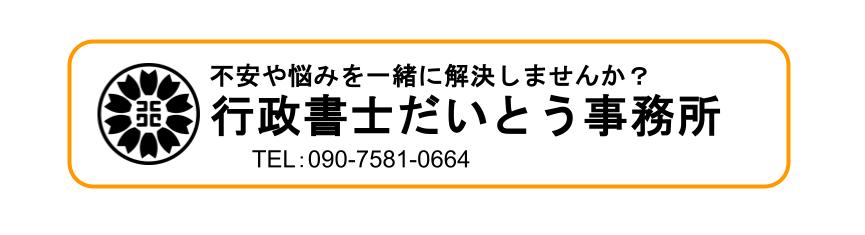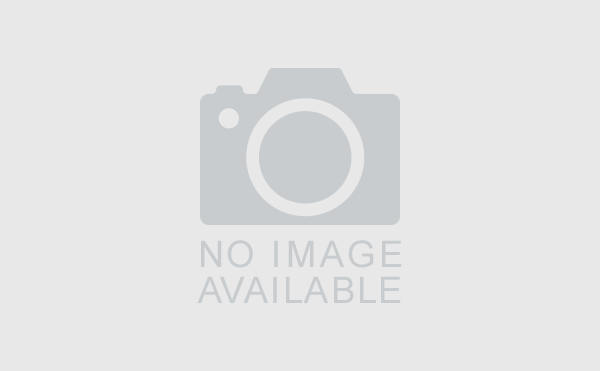遺留分とは?兄弟姉妹にはないって本当?
「遺言で全財産を長男に残す」と書いた場合でも、他の相続人が何も受け取れないとは限りません。
なぜなら、法律で最低限の取り分「遺留分(いりゅうぶん)」が定められているからです。
この記事では、遺留分の基本と、兄弟姉妹に権利がない理由を分かりやすく解説します。
遺留分とは?その目的と意味
遺留分とは、法律上、一定の相続人に認められた「最低限の財産取得分」です。
たとえ遺言で「全財産を特定の人に譲る」と書かれていても、他の相続人が生活に困らないようにするために設けられています。
遺留分は「家族の生活保障」と「相続の公平性」を守る制度です。
この遺留分を侵害するような遺言があった場合、侵害された人は「遺留分侵害額請求」を行い、金銭で補償を受けることができます。
遺留分があるのは誰?
遺留分を主張できるのは、以下の相続人に限られます。
- 配偶者
- 子(または代襲相続した孫)
- 直系尊属(父母・祖父母など)
つまり、兄弟姉妹には遺留分はありません。
兄弟姉妹は、通常、被相続人と別世帯で暮らしており、扶養関係がないことが多いため、法律上の保護対象から外れています。
遺留分の割合はどのくらい?
遺留分の割合は、法定相続分の半分が原則です。
たとえば、配偶者と子が相続人の場合、それぞれの法定相続分は1/2ずつなので、遺留分はその半分の1/4ずつとなります。
一方で、直系尊属(親など)のみが相続人の場合、遺留分は法定相続分の1/3になります。
具体的な計算例を出すと、配偶者と子がいる家庭で総財産が2,000万円なら、子の遺留分は500万円、配偶者の遺留分も500万円です。
遺留分侵害額請求とは?
遺言書で自分の遺留分が侵害された場合、相続人は「遺留分侵害額請求」をすることで権利を取り戻せます。
ただし、請求期限があり、「相続を知ったとき(遺留分を侵害されているとき)から1年以内」「相続開始時から10年以内」に行使しなければなりません。
また、請求できるのは金銭による支払いのみで、不動産などの特定の財産を直接取り戻すことはできません。
まとめ
遺留分は、家族の最低限の取り分を保障する仕組みです。
兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言によって全く相続できない場合もあります。
遺言を作成する際は、誰にどれだけの権利があるかを理解して、争いを避けるように設計することが大切です。
| 相続人 | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 全額 | 2分の1 |
| 子(孫)のみ | 全額 | 2分の1 |
| 被相続人の父母のみ | 全額 | 3分の1 |
| 被相続人の兄弟姉妹(甥姪)のみ | 全額 | 遺留分なし |
| 配偶者 子(孫) | 2分の1 2分の1 | 4分の1 4分の1 |
| 配偶者 被相続人の父母 | 3分の2 3分の1 | 6分の2 6分の1 |
| 配偶者 被相続人の兄弟姉妹(甥姪) | 4分の3 4分の1 | 2分の1 遺留分なし |