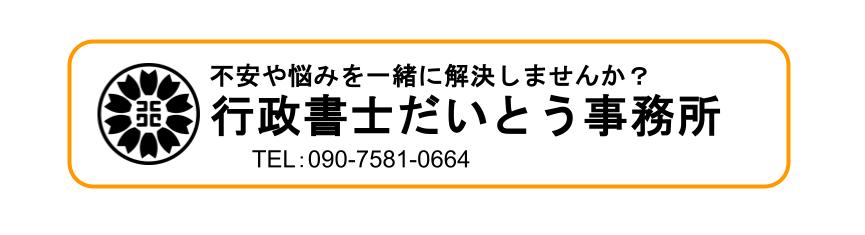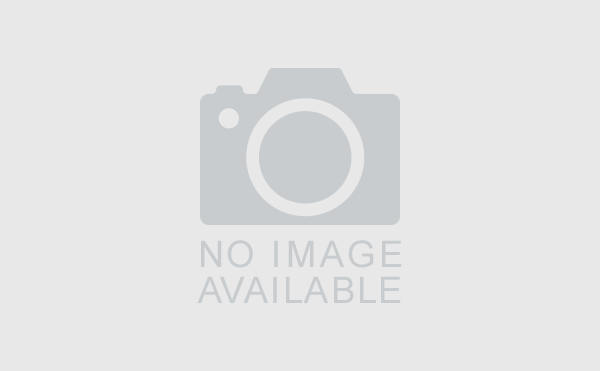在留資格とは
在留資格とは、外国の方が日本に滞在するために必要な資格のことを言います。
「どのような目的で」「どれくらいの期間」のような条件が付されています。
在留資格は、日本に滞在する資格ですが、多くの方は「ビザ」として認識しています。
「ビザ」は査証とも言われており、入国前の審査で問題がない旨の証明をするものです。
ですので、在留資格とビザ(査証)は本来異なるものですが、ホームページでは「在留資格(ビザ)と表記しています。
在留資格は全29種類あり、概要は下記の通りです。
- 一の表(就労資格)
- 二の表(就労資格・上陸許可基準の適用あり)
- 三の表(非就労資格)
- 四の表(非就労資格・上陸許可基準の適用あり)
- 五の表
- 入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
- 就労の可否と上陸許可基準の有無
一の表(就労資格)
外交
該当例:外国政府の大使、公使など
在留期間:外交活動の期間
公用
該当例:外国政府の大使館・領事館の職員など
在留期間:5年・3年・1年・3月・30日・15日
教授
該当例:大学教授など
在留期間:5年・3年・1年・3月
芸術
該当例:作曲家、画家など
在留期間:5年・3年・1年・3月
宗教
該当例:外国の宗教団体から派遣される宣教師など
在留期間:5年・3年・1年・3月
報道
該当例:外国の報道機関の職員、カメラマン
在留期間:5年・3年・1年・3月
二の表(就労資格・上陸許可基準の適用あり)
高度専門職
該当例:(1号)ポイント制による高度人材
(2号)ポイント制による高度人材
在留期間:(1号)5年
(2号)無期限
経営・管理
該当例:企業等の経営者・管理者
在留期間:5年・3年・1年・6月・4月・3月
法律・会計業務
該当例:弁護士、公認会計士など
在留期間:5年・3年・1年・3月
医療
該当例:医師、看護師など
在留期間:5年・3年・1年・3月
研究
該当例:研究者
在留期間:5年・3年・1年・3月
教育
該当例:中学校・高等学校の語学教師など
在留期間:5年・3年・1年・3月
技術・人文知識・国際業務
該当例:機械工学の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
在留期間:5年・3年・1年・3月
企業内転勤
該当例:外国の事業所からの転勤者
在留期間:5年・3年・1年・3月
介護
該当例:介護福祉士
在留期間:5年・3年・1年・3月
興行
該当例:俳優、歌手、プロスポーツ選手など
在留期間:3年・1年・6月・3月・30日
技能
該当例:外国料理の調理師、スポーツ指導者など
在留期間:5年・3年・1年・3月
特定技能
該当例:(1号)特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を要する技能を要する業務に従事する外国人
(2号)特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人
在留期間:(1号)1年以内で法務大臣が個々に指定する期間
(2号)3年・1年・6月
技能実習
該当例:(1号)技能実習生
(2号)技能実習生
(3号)技能実習生
在留期間:(1号)1年以内で法務大臣が個々に指定する期間
(2号)2年以内で法務大臣が個々に指定する期間
(3号)2年以内で法務大臣が個々に指定する期間
三の表(非就労資格)
文化活動
該当例:日本文化の研究者など
在留期間:3年・1年・6月・3月
短期滞在
該当例:観光客など
在留期間:90日・30日・15日以内の日
四の表(非就労資格・上陸許可基準の適用あり)
留学
該当例:大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、中学校、小学校の学生、生徒
在留期間:4年3月以内で法務大臣が個々に指定する期間
研修
該当例:研修生
在留期間:1年・6月・3月
家族滞在
該当例:在留外国人が扶養する配偶者・子
在留期間:5年以内で法務大臣が個々に指定する期間
五の表
特定活動
該当例:外交官の家事使用人、ワーキングホリデーなど
在留期間:5年・3年・1年・6月・3月・5年以内で法務大臣が個々に指定する期間
入管法別表第二の上欄の在留資格(居住資格)
永住者
該当例:法務大臣から永住の許可を受けた者(特別永住者を除く)
在留期間:無期限
日本人の配偶者等
該当例:日本人の配偶者・子・特別養子
在留期間:5年・3年・1年・6月
永住者の配偶者等
該当例:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
在留期間:5年・3年・1年・6月
定住者
該当例:第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人など
在留期間:5年・3年・1年・6月・5年以内で法務大臣が個々に指定する期間
就労の可否と上陸許可基準の有無
| 在留資格 | 資格 | 就労の可否 | 上陸許可基準の有無 |
|---|---|---|---|
| 外交 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | なし |
| 公用 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | なし |
| 教授 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | なし |
| 芸術 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | なし |
| 宗教 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | なし |
| 報道 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | なし |
| 高度専門職 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 経営・管理 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 法律・会計業務 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 医療 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 研究 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 教育 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 技術・人文知識・国際業務 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 企業内転勤 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 介護 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 興行 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 技能 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 特定技能 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 技能実習 | 就労資格 | 〇(活動範囲内) | あり |
| 文化活動 | 非就労資格 | ✕(原則不可) | なし |
| 短期滞在 | 非就労資格 | ✕(原則不可) | なし |
| 留学 | 非就労資格 | ✕(原則不可) | あり |
| 研修 | 非就労資格 | ✕(原則不可) | あり |
| 家族滞在 | 非就労資格 | ✕(原則不可) | あり |
| 特定活動 | △(ケースバイケース) | 活動内容による | |
| 永住者 | 居住資格 | 〇(制限なし) | なし |
| 日本人の配偶者等 | 居住資格 | 〇(制限なし) | なし |
| 永住者の配偶者等 | 居住資格 | 〇(制限なし) | なし |
| 定住者 | 居住資格 | 〇(制限なし) | なし |
在留資格は、大きく就労資格・非就労資格・居住資格と特定活動に分けられます。
上陸許可基準の有無は、入管法第7条第1項第2号イに列挙されているものを「あり」としています。
就労の可否
何らかの在留資格を取得出来ても、どのような仕事に就けるわけではありません。
就労資格は、その在留資格の活動範囲内の仕事しかすることが出来ません。
また、非就労資格は就労のために日本に来ているわけではありませんので、原則では就労をすることが出来ません。
居住資格は、基本的にどのような仕事でも就労することが出来ます。
ただ、留学生が日本に学びに来ているなかで、日本でアルバイトをすることが出来ないのでは、資金面で困窮する可能性もありますし、働くことで日本の生活を学ぶことも出来るでしょう。
そういった場合に、資格外活動許可を取得することにより、例外的にアルバイトなどで就労することが出来ます。
資格外活動許可は本業(留学など)に影響を及ぼさない程度にしなければなりませんので、週28時間以内などの条件があります。
また、風俗業や建設現場のような危険な業務は原則として禁止されています。
上陸許可基準の有無
上陸許可基準とは、外国人が日本に上陸する際に、法務大臣が定めた入国を許可するための条件をいいます。
よって、上陸許可基準がある在留資格については、在留資格に該当するだけでなく、上陸許可基準にも合致している必要があります。
上陸許可基準は在留資格により様々ですが、活動内容や学歴、契約などがあります。
上記表の上陸許可基準の有無で「なし」となっていても、法務省告示で各在留資格の基準が定められている場合があります。実質的に上陸許可基準は「あり」になります。
ですので、「外交」「公用」「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」以外の在留資格は実質的に上陸許可基準(条件)があると考えておきましょう。