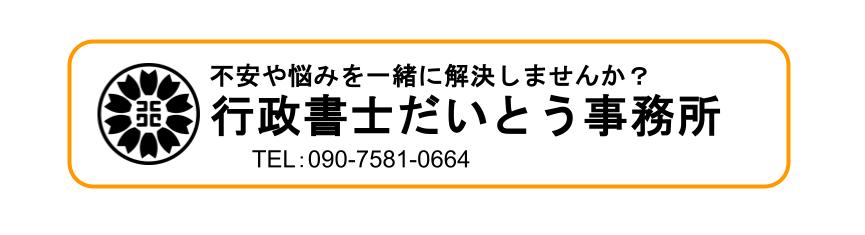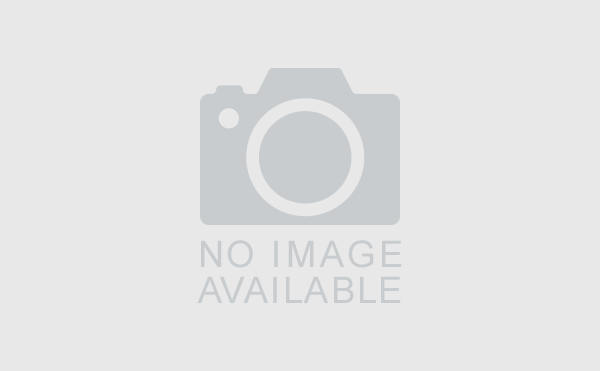特別受益・持ち戻しとは
特別受益・持ち戻しとは
特別受益とは、相続人が、被相続人から生前に受けたお金やモノなどの贈与のことをいいます。
被相続人が亡くなり、遺産分割協議を行う際に、特別受益について考えることになります。特別受益の金額により、相続分を調整して計算することになります。この計算することを持ち戻しといいます。
特別受益の持ち戻しを勘案する理由
例えば、被相続人が亡くなって、子であるAさんとBさんが相続人であるとしましょう。相続財産は4,000万円とします。
特別受益の持ち戻しをしなければ、AさんとBさんの相続分は、法定相続分に則りそれぞれ2分の1である2,000万円となるでしょう。
もし、Aさんのみが被相続人から生前に1,000万円を受け取っていたとします。Bさんからしたら「ズルい、同じ相続分は納得できない」と思うことがあるでしょう。
こういった相続の不平等を解消するために、特別受益で持ち戻しをすることになります。
先ほどの例では、相続財産4,000万円+Aさんへの生前贈与1,000万円=5,000万円をAさんとBさんで分けることになります。
相続開始時には4,000万円しか残っていませんので、生前贈与(特別受益)で調整することになります。
Aさん=(相続財産4,000万円+特別受益1,000万円)× 1/2ー特別受益1,000万円=1,500万円
Bさん=(相続財産4,000万円+特別受益1,000万円)× 1/2=2,500万円
このように特別受益の持ち戻しをすると、相続人の間で平等な相続分になります。
なお、被相続人が遺言書を作成することなどにより、持ち戻しの免除とさせることも出来ます。
特別受益の対象になるもの
特別受益の対象になるものとして、遺贈・婚姻のための贈与・養子縁組のための贈与・生計の資本としての贈与が民法で定められています。
生計の資本としての贈与について、特別受益に該当するか否かの判断が難しいことが多いです。被相続人が生前に相続人に贈与したお金が全て特別受益に該当するわけではありません。
例えば、毎月のお小遣いや食費程度であれば、通常の扶養の範囲内であると考えられるため、特別受益には該当しないとイメージ出来るでしょう。
相続人が家を購入するとのことで、被相続人がその購入資金の一部を出してあげたとすれば、特別受益に該当する可能性が高いでしょう。
他にも、生命保険金や大学の入学費用も場合によっては特別受益に該当し得ます。
特別受益に該当しそうなものをピックアップしたうえで、ケースバイケースで該当するかを確認することになりますので、大変な作業となります。
特別受益の持ち戻しを主張できる期間
令和5年4月以降に発生した相続については、相続が開始したときから10年を越えると、原則として特別受益による持ち戻しを主張することが出来なくなります。
ただし、10年以内に家庭裁判所に遺産分割の調停や審判を申し立てていれば、特別受益の持ち戻しの主張が出来ます。
これは、相続争いの長期化を防ぐ意味合いもありますので、特別受益の持ち戻しを考えている場合は、相続開始後、早めに準備して主張することが必要です。