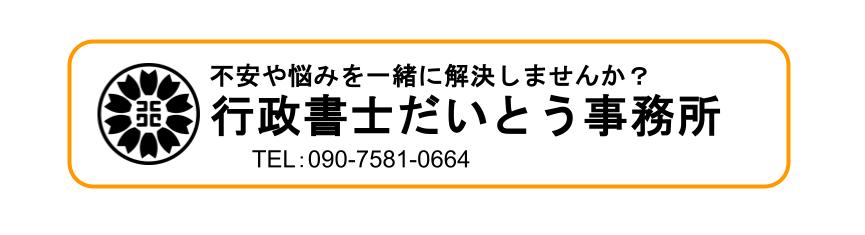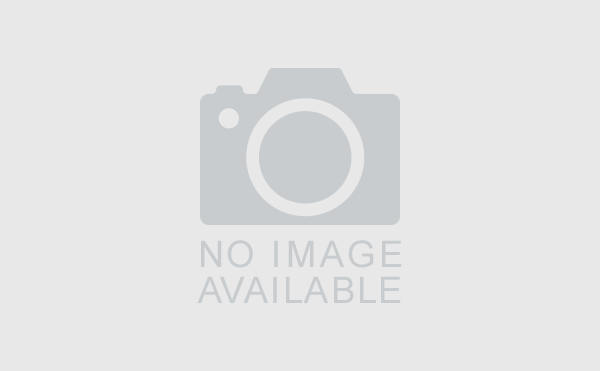対話で分かる遺言相続!(相続税編)

こんにちは!
だいとーさん!教えてください!

こんにちは!
今日はどうされましたか?

相続税ってどれくらいかかるんですか?
出来れば相続税対策をしたいと思っていまして・・・。

相続税の話ですね。
実は、行政書士や司法書士、税理士などの士業は、それぞれ専門分野がありまして、他の士業の領域に立ち入ってはならない、というルールがあるのです。
ですので、個別具体的な税金の算出については、税理士しか行ってはならないので、ここでは一般的な税金についてお話ししますね。

そんなルールがあるんですね。
はい、よろしくお願いします!

まず、相続税の基礎控除からご説明致します。
おそらく、やじろーさんも聞いたことがあると思いますが、相続税の基礎控除の範囲内でしたら、相続税はかかりません。
肝心の相続税の基礎控除の計算方法は、
「3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)」です。

あれ?そうでしたっけ?
なんか5,000万円とか聞いたことがあるような気がするんですけど・・・。

実は、平成27年1月から、基礎控除の計算方法が変わっているのです。以前は、「5,000万円+(法定相続人の人数×1,000万円)」でした。

そうだったんですね。
そもそも、変わることもあるんですね。

基礎控除の計算方法は、「今後は絶対に変わらない」と断言できるものではありませんので、あくまで現時点での計算方法であることにご留意ください。

わかりました!

さて、基礎控除の計算方法の続きですが、「法定相続人」の人数は、相続放棄をした人を含みます。
法定相続人がすでに亡くなっており、代襲相続が発生している場合は、代襲相続人の人数が、基礎控除の法定相続人の人数に加算されます。
つまり、法定相続人が配偶者と子ども1人の場合は、
「3,000万円+(600万円×2人)」=4,200万円となります。
ただ、子どもが既に亡くなっており、孫が2人いる場合は、
「3,000万円+(600万円×3人)」=4,800万円になります。

なるほど、計算自体は簡単ですね!
誰が法定相続人になるかもすぐに分かりますし。

注意しなければならないのは、相続欠格となった人や、相続廃除された人は、法定相続人の数には含まれません。

相続欠格や相続廃除は、被相続人に悪いことをした人でしたよね。そういった人の分まで相続税を軽減させてあげる必要はないですもんね。

そうですね。
先ほどもご説明しましたが、相続税の基礎控除額の計算方法は
「3,000万円+(法定相続人の人数×600万円)」ですので、覚えておいてくださいね。
あと、養子がいる場合は子どもの数え方がちょっと変わります。
まず、実子と養子がいる場合は、養子は複数人いたとしても1人までしかカウントされません。
次に、実子がおらず養子がいる場合は、養子が2人までならその人数をカウントします。よって、養子が5人いても、2人として計算されます。

わかりました!相続財産が、その基礎控除額未満なら相続税がかからないんですね!
養子も、相続税対策でたくさん養子縁組をしても思い通りにならない、ということですね。
今更ですが、相続財産ってどういったものがあるんでしょうか?

相続財産と一言でいっても、案外難しいですよね。
相続税を算出するための基になる金額を、課税価格といいます。
例えば、現金や預金、土地・建物、株式、生命保険契約に係る死亡保険金、相続時精算課税制度の適用を受けて取得した財産などが相続税を計算するための相続財産となり、金銭で評価したものが課税価格となります。

死亡保険金も含まれるのですね。
確か、死亡保険金は受取人の財産とみなされましたよね?

よくご存じですね!その通りです!
死亡保険金は、受取人の財産になるものの、相続税の計算には含めなければなりません。
ちなみに、死亡保険金などを、「みなし相続財産」といいます。相続時に被相続人が所有していたものではないものの、実質的に所有していたものとみなして、課税価格に加算されます。
また、相続時精算課税制度の適用を受けて取得した財産も課税価格に加算されます。相続時精算課税制度は「財産の取得時ではなく、相続時に税金を支払いますよ」という趣旨の制度ですので、これはイメージしやすいと思います。

なるほどね。
なかなか難しいですね。ちょっと理解が追い付かなくなってきました。
そういえば、借金などの負債があった場合は、課税価格から差し引かれるのですか?

相続税に限らず、税金については難しいですよね。そういった税金の専門家として、税理士が存在するくらいですから、一般の方にとってはかなり難しいと思います。
仰るとおり、被相続人に借金や未払いの税金などの負債があった場合は、課税価格から差し引きます。
また、葬式費用も課税価格から差し引くことになります。

流石に多額の借金が残ってて、さらに相続税も支払わなければならないとなると、相続人の負担は大きくなりますもんね。

さらにややこしいことに、生前贈与加算といって、被相続人が亡くなる日から7年間で、被相続人から贈与された財産も課税価格に加算します。
2024年1月以降に贈与される財産については、被相続人が亡くなってから7年間ですが、2023年12月以前に贈与された財産は3年間になっています。
つまり、今までは「亡くなる3年前までに贈与した財産は、相続税の課税対象です」とされていたものが、「亡くなる7年前までに贈与した財産は、相続税の課税対象です」と変更されました。

つまり、課税価格が多くなるように変更されたのですね。そして国は多くの相続税をとろうとしているわけか・・・。

残念ながら、国が定めたルールですので、私たちはこれに従うしか出来ません・・・。

でも、毎年110万円までなら贈与税はかからないんでしょう?

暦年贈与の基礎控除ですね。毎年110万円以下なら贈与税が非課税になる制度です。
しかし残念なことに、贈与税が非課税となるだけで、先ほど説明した7年以内に贈与があれば、相続税の課税対象になるのです。

そんな・・・。
なんでもかんでも税金を支払わなければならない時代ですね。

文句を言いたくなる気持ちはわかりますが、仕方がないことですので・・・。
さて、課税価格について今までのお話しをまとめると、
課税価格=(相続財産+みなし相続財産+相続時精算課税制度など)ー(負債+葬式費用)+(生前贈与加算)です。

ややこしいですね・・・。

みなし相続財産のうち、死亡保険金ってありましたよね?
受け取った死亡保険金のうち、「500万円×法定相続人の人数」までなら、相続税はかかりません。
このとき、注意しなければならないことは、被保険者と保険料支払者が同一人物でなければなりません。また、相続人以外が死亡保険金を受け取る場合は、非課税枠の適用はありません。

ということは、生前に保険に加入し、保険料を支払っておくことで、相続税の対策になるということですね!

そうです!
また、配偶者に対する相続税の軽減もあります。
これは、配偶者なら1億6,000万円もしくは配偶者の法定相続分のどちらか大きい金額までの相続財産を相続しても、相続税がかからない、というものです。
ただし、きちんと籍を入れた夫婦でないといけませんので、内縁関係にある配偶者では、この制度を利用することが出来ません。

つまり配偶者なら最低でも1億6,000万円までの相続財産を相続しても、相続がかからないのですか!
配偶者に全額相続させることも検討しないとなぁ。

この他にも、小規模宅地等の特例など、いくつか税額控除の制度がありますが、詳しくは税理士にご相談くださいね。

わかりました!

では、相続税の計算方法なのですが、実は少し手間がかかるんです。

そうなんですか?
課税価格の何パーセント、という風に算出するのではないんですか?

例えば、課税価格6,000万円、相続人が配偶者(Aさん)と子ども3人(B・C・Dさん)のケースで考えてみたいと思います。
まずは、課税価格を算出し、仮で法定相続分で案分します。
Aさんの法定相続分は2分の1ですので3,000万円、B・C・Dさんはそれぞれ1,000万円になります。

法定相続分で分けると、その通りになりますね。

この仮で求めた相続分で、下記のとおりの相続税額を算出します。
| 法定相続分に応ずる 取得価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | 0万円 |
| 1,000万円超 3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
| 3,000万円超 5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
| 5,000万円超 1億円以下 | 30% | 700万円 |
| 1億円超 2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
| 2億円超 3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
| 3億円超 6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |

計算すると、Aさんは「(3,000万円×15%)-50万円」で400万円。
B・C・Dさんはそれぞれ「(1,000万円×10%)」で100万円ですね。

では、仮で計算した相続税を一度合算します。
400万円+(100万円×3人)=700万円になります。

ここまでなら何とか計算できます!

次に、合算した相続税700万円を、実際の相続割合で配分します。
Aさんは50%、Bさんは25%、Cさんは15%、Dさんは10%の割合で相続するケースで考えてみましょう。それぞれ、いくらになりますか?

Aさんは、700万円×50%=350万円
Bさんは、700万円×25%=175万円
Cさんは、700万円×15%=105万円
Dさんは、700万円×10%=70万円
このようになりますよね?

その通りです!
基本的に、その金額が相続税になります。ここから、配偶者の税額軽減などの適用があり、実際に支払うべき相続税が算出されます。

本当にややこしいですね。
まずは相続税の基礎控除額の範囲内にあるかどうかを調べて、基礎控除額以上の相続財産がある場合は、税理士に相談するほうがいいですね!

そうですね!
やはり餅は餅屋と言いますし、税金のことについては税理士に相談することが良いでしょう。
ただ、「いきなり税理士に相談するのはちょっと・・・」という方は、行政書士に相談しても良いかもしれません。具体的な税金の計算は出来ませんが、アドバイスくらいは出来ますので!

わかりました!
ちょっと難しかったので、また改めて勉強したいと思います!
今日はありがとうございました!

また分からないことがあったら、何でもご相談ください。
出来る限り、ご回答致します!