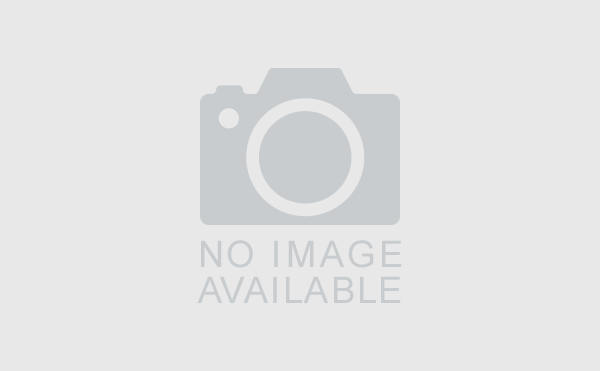法定相続人以外に財産を残したい場合は?
遺贈
相続人以外に財産を残したい場合は、遺言書を作成し、遺贈する方法があります。法定相続人以外とは、例えば子どもの配偶者やお世話になった友人などが挙げられます。子どもの配偶者から献身的な介護を受けたり、友人から多大なる恩を受けたりすると、お返ししたくなる気持ちもあるでしょう。そのような気持ちがあるのでしたら、遺言書を作成し、遺贈することを検討してみましょう。
ちなみに、法定相続人以外の人だけでなく、法人や相続人に対しても遺贈を行うことも出来ます。
遺贈とは、受贈者(遺贈を受ける人)の承諾を得ることなく、遺贈者(遺贈する人・遺言者)が一方的に行う単独行為です。なお、受遺者は遺贈を断ることも出来ますので、事前に受遺者の意向を確認しておく必要もありません。
遺言書では、「〇〇を✕✕に遺贈する。」「全財産のうち3分の1を✕✕に遺贈する。」というように記載します。前者は特定した財産を遺贈することから「特定遺贈」といい、後者は不特定の財産を割合で遺贈することから「包括遺贈」といいます。
また、「✕✕が結婚していれば〇〇を遺贈する。」などの条件も付けることが出来ます。
遺言書で「遺贈する」旨を記載しても、本当に遺贈できるか不安になる方もいらっしゃいます。相続人が「遺言書で〇〇に遺贈するって書いてあるけど、遺言書や〇〇を無視して相続人だけで遺産分割してしまおう」と考えてしまうこともあり得ます。そもそも相続人が遺言書を破棄・隠匿などをすると、その相続人は相続欠格となります。
実は、遺言書に「遺贈する」旨の記載があった場合、相続人は遺贈義務者になりますので、相続人は義務を履行しなければなりません。それでも不安になる場合は、専門家などの第三者を遺言執行者に指定する方法もあります。遺言執行者は、当然に遺言内容を実現させる義務があります(詳細は「遺言執行者の権利の義務」をご参照ください)。
受贈者は、その受けた財産により相続税を支払わなければなりません。受贈者が、被相続人の配偶者や配偶者の父母・子ども(代襲相続人を含む)でない場合は、支払うべき相続税が2割加算されます。
死因贈与
死因贈与は、上記の遺贈と異なり、遺贈者と受贈者との間で契約を結ぶことにより成立します。契約を結ぶということは、遺言書に記載するのではなく、遺贈者が生前に受贈者と死因贈与契約をすることになります。なお、死因贈与契約は口頭でも成立しますが、後々のために書面で契約することが一般的です(遺贈者が亡くなってから効力が発生するので、口頭での契約だと後からトラブルになりやすいです)。
死因贈与は、契約ですので後から撤回することも可能ですし、条件を付けることも出来ます(負担付贈与など)。
また、税金は遺贈と同じく相続税が科されることになり、受贈者が、被相続人の配偶者や配偶者の父母・子ども(代襲相続人を含む)でない場合は、支払うべき相続税が2割加算されます。