創業資金について
創業資金とは、法人や個人事業主が創業期にのみ借入することが出来る借入金のことで、一般的な借入金よりも金利面や返済期間などで優遇されていることが多いです。
一般的に、既に事業を開始している事業者よりは、融資が受けやすいとされています。創業期は実績がないことがある意味では武器になります。しかし、しっかりとした事業計画書を作成しなければなりません。また、当然に審査もありますので、融資審査のポイントも押さえておかなければなりません。
創業資金だからといって簡単に融資を受けることが出来るわけではなく、ある程度の準備も必要です。
創業資金として借入をするには、日本政策金融公庫から借入をするか、信用保証協会の保証付で金融機関から借入をするかの方法がメジャーです。
ここでは、それぞれの特徴について説明します。なお、融資限度額や金利などの諸条件は、借入申込人によって異なりますので、ここでは割愛します。
創業資金に限らず、事業資金をどこから借りるべきかを考えているのでしたら、「事業資金の調達先」もご参照ください。
日本政策金融公庫の創業資金
日本政策金融公庫は、財務省所管の特殊会社で、全国に152店舗あります。
事業内容として、国民生活事業、農林水産事業、中小企業事業に分かれています。国民生活事業は、小規模企業や個人企業向けとなっており、短期の運転資金の取り扱いもあります。なお、中小企業事業では短期の運転資金の取り扱いはありません。
日本政策金融公庫の創業資金(創業融資)は、国民生活事業に分類されています。税務申告が2期終わっていない場合は、原則として無担保・無保証での検討となります。ほかにも、利率を一律で0.65%引き下げたり、融資期間も長くしてもらえることもあります(運転資金は10年、設備資金は20年)。
ただし、金融業や性風俗業などの一定の業種では融資を受けることが出来ません。
日本政策金融公庫は、預金業務を行っておりません。ですので、口座を作成するという概念もありません。
そこで、日本政策金融公庫から融資を受けるためには、他の金融機関で口座を作成する必要があります。その口座に融資金が入金され、毎月の返済はその口座から自動引き落としとなります。
信用保証協会の創業資金
信用保証協会は、基本的に都道府県ごとに1支店あり、事業者の本社か営業所を管轄する保証協会が保証することになります。
銀行などの金融機関から融資を受けますが、保証協会が保証人になってくれるイメージです。
金融機関としても、保証協会の保証がついていればリスクの低減が図れますし、利息収入が見込めますし良いこと尽くしです。
一方、事業者(借入申込人)は、保証協会に保証料を支払わなければなりません。また、金融機関と保証協会の両方の審査を受ける必要があるので、審査時間が長くなったり、条件が厳しくなったりすることがあります。
基本的に、事業者(借入申込人)は保証協会に直接対話をすることはなく、金融機関を通して情報の伝達がなされます。
共通して気をつけなければならないこと
日本政策金融公庫で借入するにしろ、信用保証協会の保証付きで借入するにしろ、共通して注意しなければならないことがあります。
まず、嘘をつかずに正直に話すことです。後から嘘がバレると、心証が非常に悪くなります。融資を受ける前の段階なら、融資が打ち切られることもあります。
次に、自己資金です。創業するからには、ある程度の覚悟をもっているのでしょうが、自己資金を準備していないとなると、怪訝な目で見られます。自己資金は多いに越したことはありませんが、融資を受けるためには融資金の3割~4割程度を準備しておく必要があります。
なお、保証協会の創業資金では、自己資金要件がありますので、それを満たしていなければ審査すらしてくれません(創業資金はダメでも、一般資金で検討してくれることはありますが、条件面は創業資金に劣ります)。
事業計画をしっかり作成することも欠かせません。口頭で説明するよりも、書面で説明したほうが担当者に伝わりやすいです。しかし、事業計画を作ることはなかなか難しいと感じる方が多いです。伝えるべきことをしっかり伝えなければなりませんが、時間もかかるでしょう。
最後に、お金を借りるからにはきっちり返済することです。どのような事業もある程度の信頼で成り立っています。日本政策金融公庫や保証協会は、事業者のことを信頼して融資をしてくれたのです。その信頼に応えなければならない、という自覚を持つ必要があります。
まとめ
・創業資金を借りるには、主に日本政策金融公庫で借りるか、保証協会の保証付きで借りるかがメジャーな方法です。
・上記2種のうち、多くの方は日本政策金融公庫から借入をしています。
弊所では、創業資金の調達にも力を入れていますので、もし不安を感じているなら是非ご連絡ください。
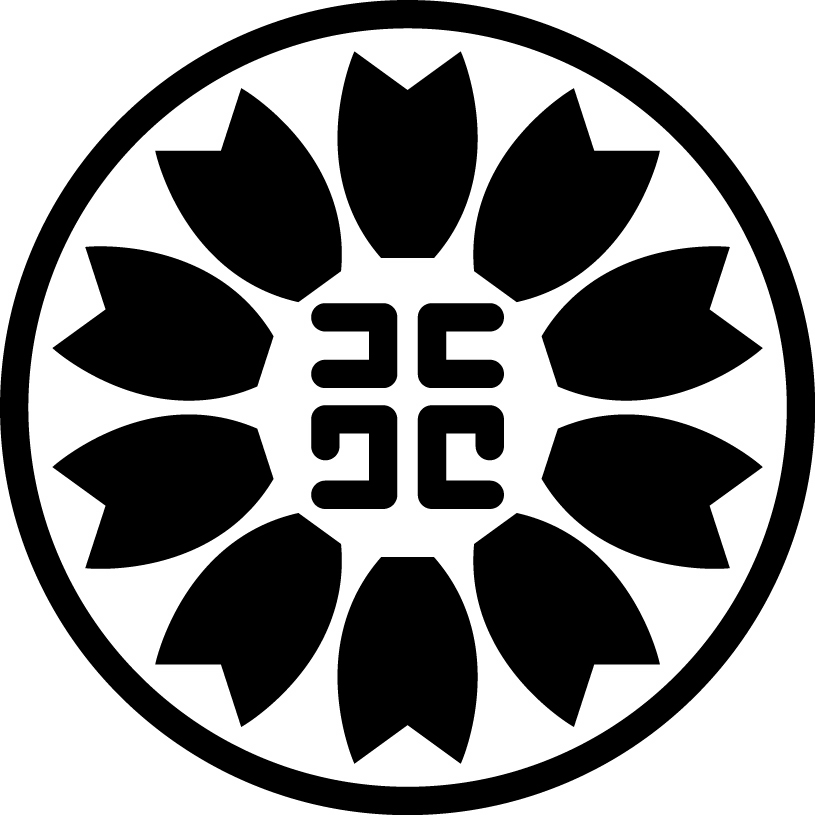
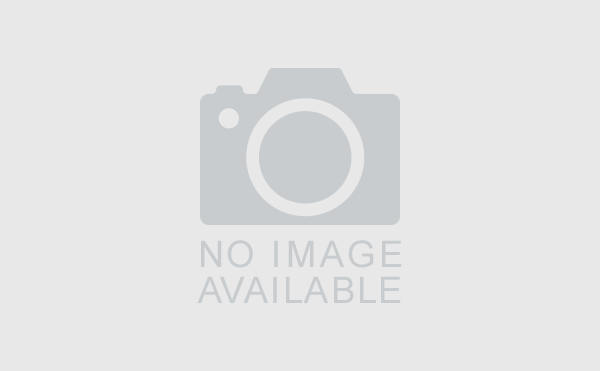
“創業資金について” に対して1件のコメントがあります。