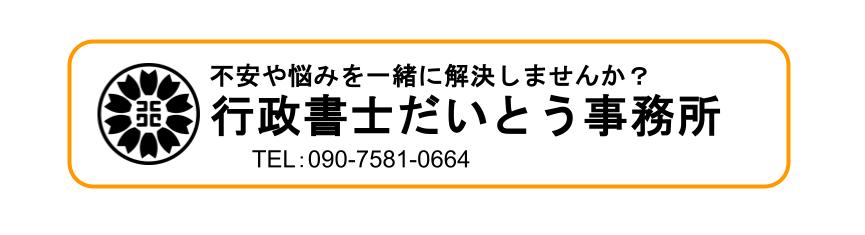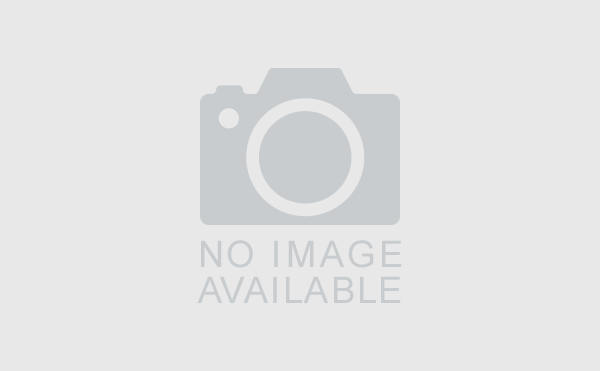遺言書を作成するタイミングはいつ?後悔しないための5つの場面
「いつか書こう」と思っていた遺言書。
しかし、実際にその“いつか”を迎える前に、判断能力を失ってしまったり、思わぬ事故で作成できなくなるケースは少なくありません。
遺言書は「まだ早い」と思ううちに準備するのが一番。この記事では、作成に適したタイミングと注意点を詳しく解説します。
遺言書を作成するタイミングは「思い立ったとき」が正解
遺言書は、体が元気なうちにしか作成できません。
認知症などで判断能力を失うと、たとえ内容を伝えたくても法的には無効になります。
また、遺言書は「一度書いたら終わり」ではなく、何度でも書き直せるのが特徴です。
したがって、「今の気持ち」を形にしておくことが大切です。
後から内容を更新できるため、完璧を目指すよりも“最初の一歩”を早めに踏み出すことが重要です。
遺言書を作成すべき5つのタイミング
① 子どもが独立したとき
子どもが社会人として独立したタイミングは、親として財産や想いを整理する良い機会です。
教育や養育の責任が一区切りし、「次は自分の老後と財産管理を考える時期」になります。
たとえば、家を誰に継がせるか、預金をどう分けるかなどを具体的に考え始めると、相続時のトラブル防止につながります。
② 不動産を購入・売却したとき
不動産は相続の中でも特に揉めやすい財産です。
家や土地を購入・売却した際には、資産の構成が大きく変わります。
「この土地は長男に」「自宅は配偶者に」など、意向を明確にしておくと後の混乱を防げます。
また、不動産を共有名義にするよりも、誰が相続するかを明確にしておく方がトラブル防止になります。
③ 会社・事業をしているとき
経営者や個人事業主の場合、事業の承継先を明確にしないと経営が止まってしまう恐れがあります。
誰に事業を引き継がせたいのか、代表権や株式の扱いをどうするのかを遺言で指定しておくことが重要です。
遺言がなければ、相続人全員の合意が必要になり、スムーズな事業継続が困難になります。
④ 再婚や家族構成が変わったとき
離婚や再婚、子の誕生、養子縁組など、家族構成が変化した際には必ず遺言の見直しを行いましょう。
特に再婚家庭では、前妻との子と後妻の子の間で相続争いが起こるケースが多く見られます。
家族の構成が変わるたびに遺言を更新することで、公平性と意向の明確化が図れます。
⑤ 病気や入院をきっかけに
体調を崩したとき、「そろそろ遺言書を」と考える方は多いものです。
ただし、病状が進行すると判断能力が不十分とされるリスクもあります。
入院中でも作成は可能ですが、証人確保や公証役場への依頼などの手続きが複雑になるため、早めの準備が安心です。
遅すぎた遺言書作成のケース
「まだ大丈夫」と思っていたら、認知症が進んで遺言が無効になったケースや、突然の事故で作れなかった事例もあります。
また、相続人同士がすでに対立している状態で遺言を作っても、信頼関係が崩れているためトラブルになりやすいのが現実です。
遺言書は“元気なうちに書く”が鉄則です。
遺言書は何度でも書き直せる
遺言は、書き直したいときにいつでも新しく作成できます。
最も新しい日付の遺言書が有効になるため、内容を更新しておけば問題ありません。
また、法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用すれば、手軽に保管・管理できます。
まとめ
遺言書は、「まだ早い」と思ううちに作るのが最も安全です。
子どもの独立や不動産取得、家族構成の変化など、“節目のたびに作る・見直す”習慣を持つことがトラブル防止につながります。
そして、内容の確認や法的有効性を確保するためには、専門家への相談がおすすめです。
判断力があるうちに書き、変化があれば見直す。この2つを意識するだけで、家族の争いは防げます。
家族や財産を守るためにも、まずは一歩踏み出して準備を始めましょう。